活動紹介
地域企業等
【授業紹介】課題解決のために「提案」し「実行」する -現場訪問とデータから読み解く新潟の今- ★学生ライター執筆記事
2023.12.12
今回ご紹介する授業は「現場訪問とデータから読み解く新潟の今 -新潟地域産業の可能性を探る-」(経済科学部「課題演習B」「社会開放演習B」との同時開講)です。本授業では、2022 年度から新潟県央地域の三条市をフィールドの 1 つとして活動しています。
新潟の地域産業が抱える課題の一つとして「若者の人材不足」があります。この三条地域での活動では、その原因と課題を若者の「価値観」や「行動パターン」に沿って解決することを目的とした企画を考案します。そして、考案した企画を実際に実現することで、若者と企業を結ぶよりよい繋がりとなることを目指していきます。
高校や大学の授業で、企業に対して何かを「企画・提案する」経験は存在するかもしれませんが、その企画を「実行」まですることはあまりないかと思います。
9月28日に行われた中間報告会では、受講生15名に加えて、学生の企画をサポートして下さる三条市役所や地域おこし協力隊の方3名が参加されました。本記事では、この報告会に参加し、企画実行までの道筋をイメージする様子を取材してきましたのでご紹介します。
当日は学生3グループから企画の提案がありました。
①新大祭(新潟大学の学園祭)での、三条ものづくりブースの出展
②学生のプロフィールを基に、企業側が自社に合った学生を見つけられる仕組み
③三条の企業と新潟大学生との食事会
「若者の人材不足」を解消するという課題1つをとっても、グループでその一番の原因と考えるものとその解決方法が異なっていて、聞いている側としてはとても興味深く、グループ活動の利点であるなと感じました。
そして昨年提案したプロジェクトを今年実行する段階にある2年目の受講生からは、その成果発表や進捗報告がありました。
①Uターンをまだ考えていない学生にも地元の企業を知ってもらうための、帰省に合わせた「企業0円バスツアー」(実施済み)
②企業と若者をつなげる長期インターンシップを実施するための「マッチングイベント」(企画進行中)
会の後半では、この1年目・2年目の受講生に、三条市役所や地域おこし協力隊の方々を交えて、今年の受講生の提案を実践していくための意見交換が行われました。


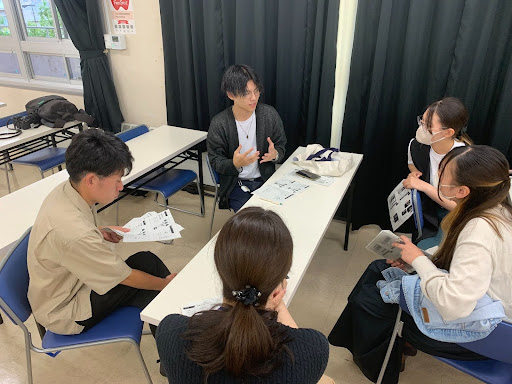
提案を実践に移していくにあたっては、予算をどうするか、参加者はどのように募っていくか、企画をどのように宣伝していくかなどの課題があります。2年目の受講生からは、自身の経験を踏まえて、特に気をつけて企画を進めていく場面や、提案の中で抽象的なところは他の事例を参考にしながら具体化できるようにすることなどのアドバイスがありました。特に1年目の受講生にとって、今後のアクションを明確にするための意見交換がなされていたと思います。企画実行をサポートして下さる三条市地域おこし協力隊の鴨井さんも、今回の企画提案が、企業に取り入れてみたい、協力したいと思えるものであったとおっしゃっていました。
今回の取材では、課題解決のための企画提案の段階でしたが、今後の授業では実際にその企画を「実行する」という段階に入っていきます。
企画をするだけであれば、中身があまり練られていないものであったり、アプローチする対象がずれていたりしても、「授業内容に沿った企画」であれば案として評価されることもあります。しかし、企画を実行していくにあたっては、当然責任を伴います。そのため、どこか一つでもアラがあっては企画を進めることができません。提案を吟味していく中で、本来やりたいこととずれてしまったり、逆にやりたいことを詰め込みすぎてしまったりなど苦労する場面が多かったと、2年目の受講生や地域の方々もおっしゃっていました。
ここで企画された提案がどのような内容に進化し、実現していくのか、今後の活動に注目していきたいと思います。
【本件に関するお問い合せ先】
学務部教務課連携教育支援事務室
Email renkeikyoiku(at)adm.niigata-u.ac.jp
※(at)を@に置き換えてください
新潟の地域産業が抱える課題の一つとして「若者の人材不足」があります。この三条地域での活動では、その原因と課題を若者の「価値観」や「行動パターン」に沿って解決することを目的とした企画を考案します。そして、考案した企画を実際に実現することで、若者と企業を結ぶよりよい繋がりとなることを目指していきます。
高校や大学の授業で、企業に対して何かを「企画・提案する」経験は存在するかもしれませんが、その企画を「実行」まですることはあまりないかと思います。
9月28日に行われた中間報告会では、受講生15名に加えて、学生の企画をサポートして下さる三条市役所や地域おこし協力隊の方3名が参加されました。本記事では、この報告会に参加し、企画実行までの道筋をイメージする様子を取材してきましたのでご紹介します。
当日は学生3グループから企画の提案がありました。
①新大祭(新潟大学の学園祭)での、三条ものづくりブースの出展
②学生のプロフィールを基に、企業側が自社に合った学生を見つけられる仕組み
③三条の企業と新潟大学生との食事会
「若者の人材不足」を解消するという課題1つをとっても、グループでその一番の原因と考えるものとその解決方法が異なっていて、聞いている側としてはとても興味深く、グループ活動の利点であるなと感じました。
そして昨年提案したプロジェクトを今年実行する段階にある2年目の受講生からは、その成果発表や進捗報告がありました。
①Uターンをまだ考えていない学生にも地元の企業を知ってもらうための、帰省に合わせた「企業0円バスツアー」(実施済み)
②企業と若者をつなげる長期インターンシップを実施するための「マッチングイベント」(企画進行中)
会の後半では、この1年目・2年目の受講生に、三条市役所や地域おこし協力隊の方々を交えて、今年の受講生の提案を実践していくための意見交換が行われました。


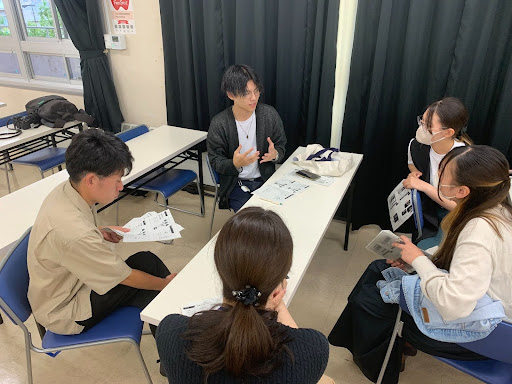
提案を実践に移していくにあたっては、予算をどうするか、参加者はどのように募っていくか、企画をどのように宣伝していくかなどの課題があります。2年目の受講生からは、自身の経験を踏まえて、特に気をつけて企画を進めていく場面や、提案の中で抽象的なところは他の事例を参考にしながら具体化できるようにすることなどのアドバイスがありました。特に1年目の受講生にとって、今後のアクションを明確にするための意見交換がなされていたと思います。企画実行をサポートして下さる三条市地域おこし協力隊の鴨井さんも、今回の企画提案が、企業に取り入れてみたい、協力したいと思えるものであったとおっしゃっていました。
今回の取材では、課題解決のための企画提案の段階でしたが、今後の授業では実際にその企画を「実行する」という段階に入っていきます。
企画をするだけであれば、中身があまり練られていないものであったり、アプローチする対象がずれていたりしても、「授業内容に沿った企画」であれば案として評価されることもあります。しかし、企画を実行していくにあたっては、当然責任を伴います。そのため、どこか一つでもアラがあっては企画を進めることができません。提案を吟味していく中で、本来やりたいこととずれてしまったり、逆にやりたいことを詰め込みすぎてしまったりなど苦労する場面が多かったと、2年目の受講生や地域の方々もおっしゃっていました。
ここで企画された提案がどのような内容に進化し、実現していくのか、今後の活動に注目していきたいと思います。
【本件に関するお問い合せ先】
学務部教務課連携教育支援事務室
Email renkeikyoiku(at)adm.niigata-u.ac.jp
※(at)を@に置き換えてください